経済学部の岡本ゼミが昨年度「しあわせの村」活性化プロジェクトに取り組みました
2025/07/02

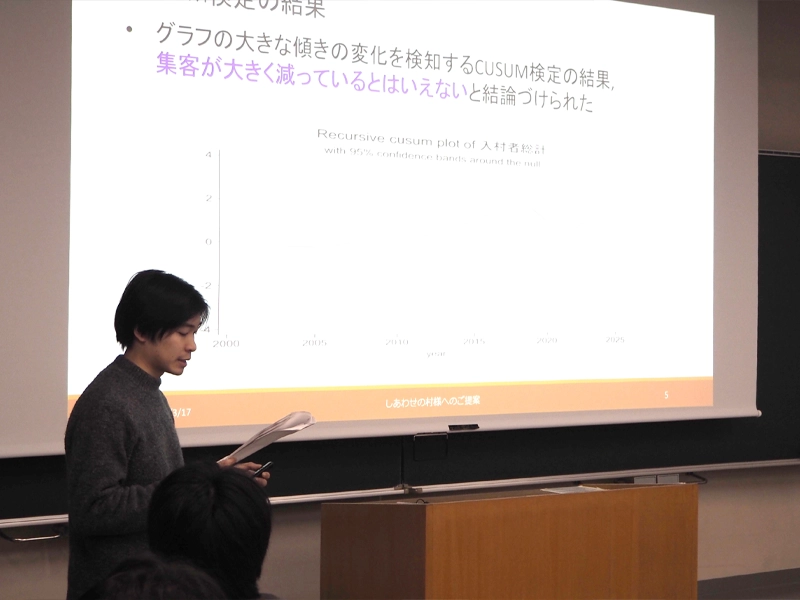

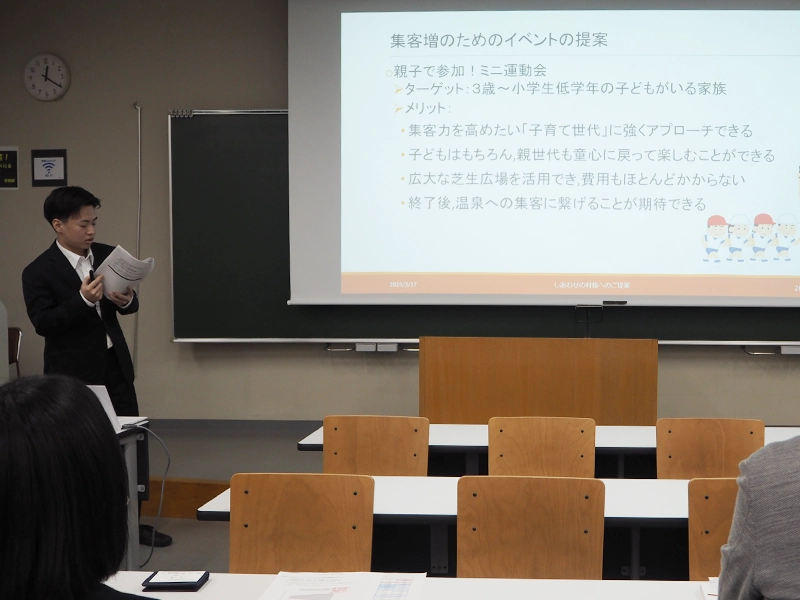
、田中さん(中央右)と記念撮影する岡本ゼミ生.webp)
経済学部の岡本弥准教授のゼミは、昨年度の3年次生(現4年次生)が同年4月より、データ分析を活用した企業等の課題解決に取り組みました。今年3月17日に「しあわせの村」活性化プロジェクトの最終プレゼンを実施して終了しました。
「しあわせの村」は1989年にオープンし、神戸市民にはよく知られる総合福祉施設です。甲子園球場が約50個も入る広大な敷地には、高齢者や障がい者の自立を援助する福祉施設のほか、運動広場や芝生広場、宿泊施設、温泉施設もあり、近隣の人々の憩いの場として機能するとともに、「フロントランナーとしての市民福祉を実現する場」「多様な市民が集い交わりにぎわう場」「ソーシャルインクルージョンを実現する拠点」として存在感を発揮しています。
本プロジェクトでは、連携協定を提携しているこうべ市民福祉振興協会のコロナ禍以降における課題について、ゼミ生が要望や期待に応えるべく、データ分析による客観的な課題解決を目指し活動を進め、日々、議論とデータ分析を積み重ねました。
昨年5月に初めて訪問し、「しあわせの村」の運営主体である同協会の佃孝司課長、高田明弘係長、田中涼帆氏の話を聴き、各施設を見学しました。
その後、現地ヒアリングで得た情報を持ち帰り、今後の方針を話し合った結果、要望のあった①新たな福祉企画の提案のほか、より多くの人々に「しあわせの村」のよさを体感していただくため②「しあわせの村」の利用者数の分析、③同利用者満足度の分析を「課題解決」を柱に設定しました。
②と③については、長期にわたる施設ごとの集客データや、利用者を対象に行われたアンケート調査データなど精度の高い分析を行う上で不可欠となる情報も快く提供していただきました。
今年3月の最終プレゼンでは、まず、高畑翔さんがプレゼンの進行について説明し、利用者数分析班(花咲優気さん、大坪琉生さん、外村龍也さん、村上大喜さん)が報告を行いました。
新型コロナが発生した直後に一時的に客足が落ち込んだものの、現在では概ね回復していますが、20年以上にわたって蓄積された利用者数データを時系列解析した結果からも、全般的な集客力が低下したとは言えないことがわかりました。ただし、利用者数の90%以上を占める神戸市の人口構造は近年、大きく変化しており、なかでも、「しあわせの村」にとって「リピーター層」と認識されてきた25~39歳の「子育て世代」の人口が減少していることが、子どもや若年層の来客者数減少につながっている可能性を、因果関係を検証するグレンジャー因果検定の結果から指摘しました。
続いて、利用者満足度分析班(高畑翔さん、立巳隆規さん、行天弘武さん、木村颯さん)が、満足度に影響を与える要因の検証結果を報告しました。順序プロビット分析を用いた分析から、(A)子どもや若年層(B)水・木・金曜日の利用者(C)無料シャトルバスで訪れる利用者(D)「宿泊施設」、「トリム園地(子ども向けアスレチック施設)」、「テントキャンプ場」「ボウケンノモリ(有料子ども向けアスレチック施設)」の各利用者が、より大きな満足度を得ていることが明らかとなりました。このような結果を踏まえ、「子育て世代」に対してより強くアピールする重要性から、親子で参加可能な「ミニ運動会」の開催を提案しました。
最後に、新たな福祉企画としては、健常者と障がい者が協力して、手芸でイルミネーション作品を制作しクリスマスの時期に展示する、というイベントを提案しました。
報告終了後、佃課長は「魅力的な提案であり新たな福祉企画として検討したい」と述べ、岡本准教授は「佃課長ほかしあわせの村の方々に、1年間ご協力頂き大変感謝しています」と話しました。
