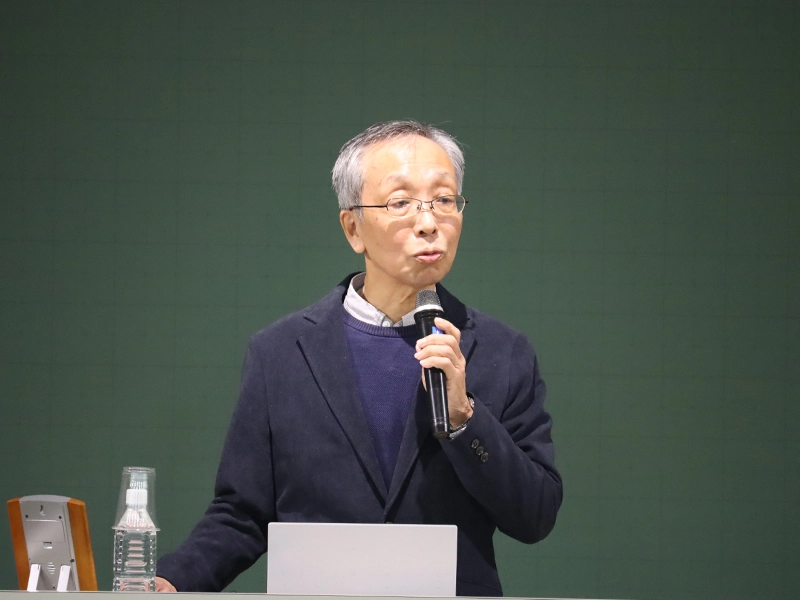土曜公開講座「健やかなくらしを守るために認知症を正しく理解しよう」を開催しました
2025/11/26
心理学部の博野信次教授による土曜公開講座「健やかなくらしを守るために認知症を正しく理解しよう」を11月15日にポートアイランド第1キャンパスにて開催し、124人が受講しました。
土曜公開講座は今秋で第90回目の開催となり「私たちのくらしと文化」という統一テーマに基づき、各研究分野の教員が全6回の講義を行っています。
はじめに博野教授は、認知症について「一旦獲得された認知機能が、脳の疾患により、広範囲に、遷延性に、障害された状態を指す」と定義し、疾患名ではなく障害の名称であると説明しました。また、認知症を引き起こす疾患は多岐にわたり、アルツハイマー病、出血や梗塞が原因となる脳血管障害、その他脳疾患として脳腫瘍、ビタミン欠乏症、脳炎などが含まれると解説しました。
症例として、物忘れ、見たものがはっきりわからないという症状で来院した80代の女性について紹介。画像診断の結果、脳腫瘍を発見し、認知症に対する治療法の確定に至ったことから、疾患によって異なる治療法を導き出すための診断が重要であると説明しました。
さらに1970~80年代までの日本では、脳血管障害による認知症が最も多く、その主要な要因としては、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常、心臓病(心房細動など)などの危険因子が、動脈硬化を悪化させるという知識が浸透していなかった事が主な原因であると解説。これらの危険因子を管理することが、脳血管性認知症の予防に有効であると述べました。
また、アルツハイマー病は、エピソード記憶障害(いつ、どこで、何をしたかという記憶)から始まり、その後、意味記憶、言語、視覚認知などの認知機能が徐々に低下し、末期になると、運動障害、排泄障害などが起こると解説しました。アルツハイマー病の根本的な予防法、治療法は確立されておらず、症状の進行を遅らせるためには、「健やかなくらし」が重要であると述べました。
「健やかなくらし」の具体例として、認知機能の低下や認知症の発症リスクを低減するためには、認知活動や身体活動を通して社会への積極的な参加が重要であると説明。認知活動を向上させる方法として、文字の読み書きや将棋などのボードゲーム、楽器の演奏や料理などを挙げ、身体活動として週2回以上の筋力トレーニングやウォーキングなどの有酸素運動が効果的であると紹介しました。ただし、嫌いな活動を強制すると、むしろ逆効果になる可能性もあると注意点についても呼びかけました。
その他、効果的な食事方法についても解説し、特に地中海食に多く見られる果物、野菜、魚類やナッツ、オリーブオイルなどの組み合わせが効果的であると紹介しました。文化が大きく異なるわが国では、地中海食を導入することは難しいが、主食、主菜、副菜をバランス良く摂取する意識が重要であり、多様な食品を組み合わせた食事法が効果的であると補足しました。
博野教授はまとめとして、「適切な食事法、禁煙、飲酒制限や生活習慣病の適切な治療管理など、総合的に健康管理を行い、健やかなくらしを送ることが重要である」と述べ、講義を締めくくりました。
参加者は「認知症予防に有効な生活方法を知ることができて良かった」とのコメント。10代の女性は「将来は福祉施設で働きたいと思っているため、認知症について理解を深めることができて良かった」といった感想を寄せました。
次回は、11月29日に心理学部の難波愛准教授による「子育て・孫育てを楽しむ! カウンセリングの知恵袋」を開催します。