さまざまな側面からの「言葉」の学びが
未来の良好な人間関係や仕事を導く


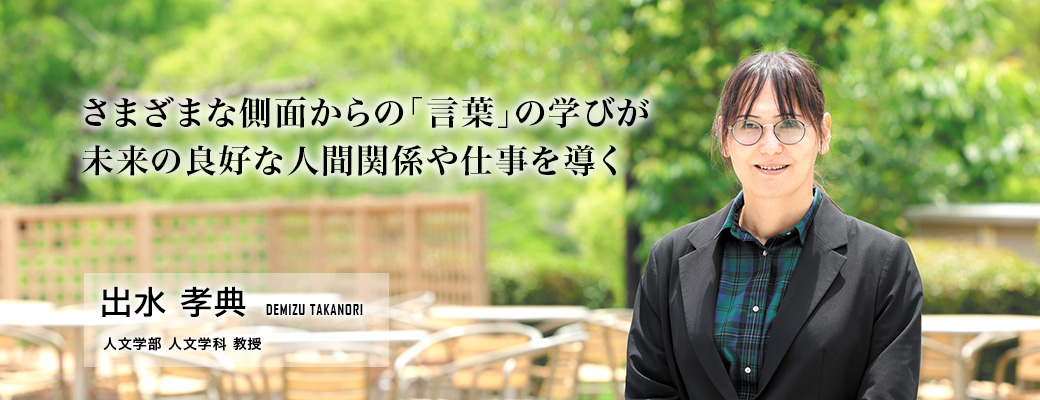
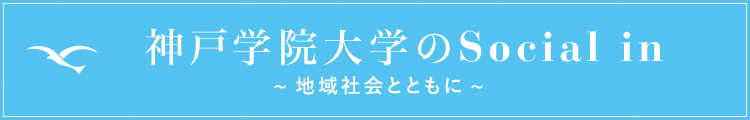

豊富な具体例と独自の視点を取り入れ、初学者にもわかるように工夫を凝らした著書『語彙アスペクトと事象構造』が
第24回英語語法文法学会賞を受賞

私の専門は言語学の「語彙意味論」という分野で、主に英語の動詞が持つ意味について研究しています。大学院で師事していた児玉徳美先生の授業で、移動を表す動詞にはwalkのように様態を表すものと、arriveのように結果を表すものがあり、言語によってそれらの使い方が異なるということを学んだことが“様態”と“結果”の違いに着目するきっかけでした。純粋に「おもしろい」と興味を持ったことから私の研究人生が始まったのです。そして、様態と結果を表す動詞について研究を進め、博士論文を執筆して今に至ります。
2023年秋には、著書である『語彙アスペクトと事象構造(上)(下)』について第24回英語語法文法学会賞を受賞することができました。この「語彙アスペクト」は動詞の表す事象の時間的性質のことを意味し、「長く続く・一瞬で終わる」の違い、「決まった終わりがある・ない」の違いがそれにあたります。例えば、「パソコンを叩いた」の「叩く」。これは何度でも叩けますよね。ここには決まった終わりがありません。でも、「壊す」の場合は一度壊れてしまったら、それ以上壊すことはできません。ここに「続ける」という単語を付けてみると、「(パソコンを)叩き続けた」とは言えますが、「(パソコンを)壊し続けた」とは言えない。一台のパソコンを壊し続けることはできませんので、ここには“決まった終わりがある”ということになります。このように、動詞の表す事象の時間的性質である「語彙アスペクト」と、長年研究してきた動詞の意味構造を関連付けてまとめたものがこの本です。
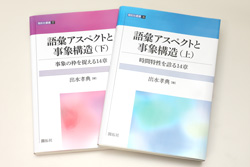
今回の受賞では、豊富な具体例を使って理論をわかりやすく説明しながら既存の理論を紹介するだけでなく、複数の理論をオリジナルな形で結び付けて説得力のある枠組みを提示した点が評価されました。上巻は、語彙アスペクトと呼ばれる時間的性質を理解するためのトレーニングとしての役割を担っており、小説などから集めた例を豊富に挙げています。それを踏まえた下巻では、様態や結果などの事の有り様や事象構造と結び付けていますが、ここでも具体例を多く挙げているのが特徴です。いずれも理論を具体例で説明して理解を促す内容になっており、専門書でありながら概説書も兼ねています。予備知識がない方でも目を通していただければ、(わからないことはインターネットで少し検索しながら)ご自身でも語彙アスペクト等に関する論文を書けるようになる。そんなことを狙って書き進めました。読まれた方の感想は、「例が豊富でわかりやすい」というものが多いですね。「説明がくどい」というようなご意見もいただきましたが、あえてくどく書いております(笑)。
言葉についていろいろな側面から学ぶことで、気配りができ、物事をうまく伝えられるように成長を
学生には、英語を一緒に読んでどう日本語に訳すのかというワークを通して“言葉”について考えてもらっています。例えば、英語のbeautiful=日本語の「美しい」だとよく思われていますが、英語小説の日本語訳でよく「きれい」と訳されているのはどうしてなのか。学生には、言葉についていろいろな側面から学ぶことで、少しでも言葉をうまく使えるようになってほしい。そして、将来自分で文章を作成する際にもさまざまな気配りができるようになり、人にうまく物事を伝えられるように成長してほしいと願っています。
そのためにも、表現の間接性・直接性の問題について研究し、授業やゼミで教えています。例えば、窓を開けてほしい時に普通は「窓を開けてください」と命令文で言いますよね。でも、「窓を開けることはできますか?」と疑問文にしたり、「窓を開けてもらえると有難いのですが」と平叙文で言ってみたりすることもあると思います。これは、本来の働きとは異なる言葉の使い方をすることで遠回しに伝えているのです。他にも、デート中に彼女が彼氏に「●●君、これ買って」と言うよりも、「●●君にこれ買ってもらえたら私、嬉しいな」と言う方が押しつけがましくないですよね(笑)。実際に、そのような言葉は小説や映画などのセリフでも多用されていますし、一部の学生はJ-POPの歌詞やドラマ、漫画、アニメなど自ら好きな題材を選び、そこで使われている言葉を分析して卒業研究にまとめています。
実は、人は仲良くなればなるほど直接的な言い方をするもの。カップルになった当初と別れの時期は言葉の使い方が異なります。ゼミでは恋愛映画の例を挙げることもあります。身近な題材を使って表現方法を具体的に学ぶことで、将来仕事に就いた時、より適切に言葉を使えるようになってほしいですね。
さらに、ジェンダーと言葉については、“女ことば”とされるものの特徴と、それが小説や映画の台詞など創作物にどううまく使われているのかを授業で取り上げています。例えば、ネコ型ロボットのアニメに登場する女の子は「~してみたいわ」「やだわ、●●さん」などという、現代では使わないような女ことばを使っています。反対にガキ大将の男の子は「~だぜ」「~するぞ」というような話し方をしている。これは登場人物の“キャラ付け”に役立っていますが、女らしさ・男らしさを意図的に演出するために“文末助詞”が効果的に使われているのです。日本語での文末助詞は特に性差を表現しやすいもの。そんなことも授業でお伝えしています。
音楽アーティストによっては、女性が女ことばで歌ったり、中性的な言葉で歌ったりしている場合もあります。特にどんな文末助詞を使っているかを調べると、アーティスト毎の傾向も出てきます。例えば、文末に「~だろう」が多い歌手、「~さ」がよく出てくるバンド、「~かな」が頻繁に出てくる歌手もいます。このように文末に着目するといろいろわかってくるんです。それぞれの個性を表す言葉の使い方から一体、何が読み解けるのか。これを学生に考えてもらうことで卒業研究につながることもあります。自分の好きなアーティスのことだと真剣に取り組みやすいですよね。
英語小説とその翻訳について、日本語や他言語では様態と結果がどう表現されているのかを研究したい

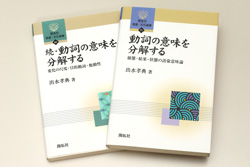
以上のように、学生には“言葉”について取り上げるという前提で卒業研究を書いてもらっていますが、私のゼミでは言葉に関する分野に共通する論文の書き方について、自作のテキストとともにゼミで教えるようにもしています。例えば、論文などからの引用の仕方、データ分析した後の考察の書き方、構成の方法などを伝えて、わからないことはテキストを確認しながら進めてもらうという方法をとっています。もちろん英語の動詞について書く学生もいますが、テーマは“言葉”という軸で幅広く設定している分、学生が研究する内容は多岐にわたります。このように、卒業研究の書き方を体系的にまとめることでベースの整った論文を書ける学生が増えてきました。“言葉”に興味を持つ学生は自分のこだわりを持っていることが比較的多いと感じるからこそ、自分のこだわりからつながる興味のあることを深掘りしてほしいと願っています。
言葉の研究というものは地道で愚直なものです。何が出てくるのかわからないのに、まずはデータや例を集める。そこから“共通点と差異”を見つけ出す。このような地味な作業が必要ですが、それらを繰り返して卒業研究としてまとめることが、例えば会社に入って何かを企画したり、分析して文章を作ったりする際に役立つと私は考えています。また、間接表現を使って文書を作ったり、ジェンダー的表現を極力避けたりすることで、社会人としてうまく生活できるようになってほしいです。
私の今後の研究としては、英語小説からの実例とその翻訳を参照することで、日本語やフランス語、ドイツ語、中国語などで様態と結果がどのように表現されているのかを、さまざまな動詞を取り上げて調べていきたいと考えています。例えば、英語の小説内に出てくる単語Aが、翻訳された中国語では単語Bになっていたり単語Cになっていたりします。訳され方の違いを調べることで、一つの単語がなぜいろいろな意味で使われているのか、その動機付けは何であるのかということなどを研究していきたいです。また、英語の様態動詞が他言語では結果動詞になっているようなケースもあり、そこにはどのような解釈の違いが生じているのか。そのようなことを小説の原文や翻訳から見つけ出したいと思っています。
Focus in Lab

ゼミ生と一緒に英語を読み、日本語に訳すことで言葉について考えてもらっています。また、英語の動詞に関する卒業研究だけでなく、J-POPの歌詞の文末表現や、ドラマ・漫画・アニメなどの台詞に見られる表現の間接性・直接性の問題、ジェンダーと言葉についての研究をして発表するゼミ生もいます。その発表に対して皆で考えたり、私が指導したりすることで“言葉”の学びを深めています。
プロフィール
学歴
| 1995年 | 立命館大学 文学部 英米文学専攻 卒業 |
|---|---|
| 2000年 | 立命館大学 文学研究科英米文学 博士後期 単位取得満期退学 |
| 2014年3月 | 文学博士(立命館大学) |
経歴
| 1997年 -2000年 |
立命館大学 文学部 文学科 英米文学 専攻助手 |
|---|---|
| 2003年 -2008年 |
立命館大学 言語教育センター 外国語嘱託講師 |
| 2008年 -2017年 |
神戸学院大学 人文学部 人文学科 准教授 |
| 2017年- | 神戸学院大学 人文学部 人文学科 教授 |
