模擬国連のアドバイザーとして
学生の視野を広げ、成長を支える



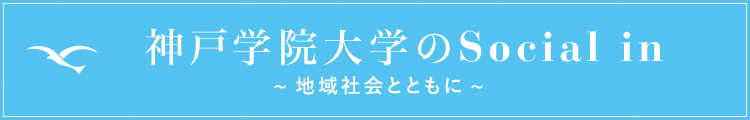

大学では英語を“使う”ことで課題解決等に取り組む

私はイギリスで大学院まで進み、日本へ来たのは2006年。もうすぐ20年になります。当初は英会話学校の講師として、その後は日本の大学生に対して英語教育を行ってきました。日本の学生は高校まで英語の文法を中心に学びますが、大学では“英語を使う”ことを大切にしてほしい。その想いをもとに授業や研究、さまざまな活動を行っています。
皆さんは、教育心理学者のベンジャミン・ブルーム氏によって1956年に作成された「ブルームのタキソノミー」をご存知でしょうか。これは、難易度が異なる6段階の目標を達成していくことで学習を進めるという教育フレームワークです。日本の中学や高校では、第1段階の「知識」にフォーカスすることが多いですが、大学ではより高度な「分析」「評価」というところまで到達してほしい。つまりは英語を学ぶだけではなく、英語を使ってさまざまな事象について考えたり、課題解決に取り組んだりしてもらいたいと思っています。これは、私が研究を続けている「クリティカル・シンキング(物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること)」教育を考えるうえでも重要な指標となっています。

また、「第2言語の効果」についての研究も行っています。例えば、倫理学や哲学等の分野でよく議論される思考実験のひとつ「トロッコ問題」。制御不能になったトロッコが線路上にいる5人の作業員に向かって突進しており、あなたはその近くでレバーを操作できるとします。その際、レバーを引いて5人の作業員を助け、1人の作業員を犠牲にする。もしくは何もしないことで5人を犠牲にし、1人を助ける。皆さんはどちらを選びますか?私の研究では、この問題を第1言語で聞いた時に「私は関わりたくないからレバーを引きません」と答える傾向が高まり、一方で、第2言語の時は「(犠牲者の数を比べて)レバーを引く」と答える傾向がやや高くなりました。一般的に第1言語では“感情”と結びつきやすく、第2言語では“理論的な考え方”と結びつきやすいと言われますが、まさにこれに通じる結果となったのです。このような「第2言語の効果」の研究を今後も続けていきたいですし、使う言語によって考え方が変わるということを学生にも知ってもらいたいと思っています。
「日本英語模擬国連」での経験を通じて、自分とは異なる考え方を知ってほしい

大学生を対象とし、会議の準備から本番の運営まですべてを学生主体で行う「日本英語模擬国連(JEMUN)(※以下、模擬国連)」。模擬国連とは、参加者が各国の⼤使になりきり、実際の国連の会議や国際会議を模擬する活動です。この大会は2010年に始まって以来、日本国内だけでなく海外からの参加者も多く迎えて開催されてきました。模擬国連では会議ごとに議題が設定されており、⼈権や軍縮、経済、環境、紛争などと⾮常に多岐にわたる国際問題が取り上げられます。それらの議題に対して、参加者は会議準備として担当国の政策や歴史、外交関係などを調べ、その過程で得た知識や情報をもとに⾃国の政策を作ります。その後に⾏われる会議では、各国の⼤使という⽴場から考えた政策を軸に議論や交渉、スピーチなどを⾏っていきます。私はこの模擬国連において、本学の学生に対するアドバイザーと大会におけるアドバイザーの両方を担当しています。

2024年の模擬国連には国内外の22大学から237人の大学生が参加。本学からは10人の学生が参加し、各国大使とジャーナリストの役を務めました。そこでは「持続可能な観光の実現」について話し合いましたが、それぞれの学生は「大使」という立場ですから、日本人の考え方とは異なる意見が必要です。そのため、まずは事前に各国の状況を知るというところが重要で、それに対してどんなアプローチが有効かということを考えるプロセスへと進みます。ここでは、情報がありすぎる・なさすぎるというケースがあります。例えば、本学の学生が担当した「ニカラグア」の知りたい情報を探してもほとんど出てきませんでした。そのような時には、「国連のウェブサイトを利用しましょう」とアドバイスしています。世の中には間違った情報も多くありますので、正しい情報を得る重要性も伝えるように心がけています。
私がこの模擬国連のアドバイザーとして学生の皆さんにいつも話しているのは、「自分の立場以外の考えを知る」ということ。自分が当たり前だと思っていることは他国の人にとっては当たり前ではない可能性があります。例えば、日本では普通に飲める水も、他の国では飲めないかもしれないですよね。そのような状況の違いや考え方の違いを知り、受け入れること。これを大切にしてほしいと願っています。2025年のテーマは「教育」。模擬国連は夏に開催されますので春から準備に取りかかりますが、新1年生にもぜひチャレンジしていただきたいですね。

なお、議題に対する自国の立場や政策、それらを支える論理を述べる「ポジションペーパー」については、本学の学生が、2022年と2023年の2年連続で「ベスト・ポジションペーパー賞」を受賞。国内外から参加した24大学のうち最も活躍した3大学に贈られる「ポジティブ・インパクト大学賞」を本学が2023年に受賞するなど嬉しい結果が出ています。
模擬国連に参加したどの学生にも成果があります。例えば、ディベートは難しくてなかなかついていけなかった学生から、「モーション(会議進行や手続きに関する提案)を出すことができて良かった」という感想が出たり、所属している学部以外や本学外の学生と知り合って交流の輪が広がったりすることも稀ではありません。なにより、この経験を通じて自信がつき、さまざまな学びや活動を行う意欲が生まれていることを誇りに思っています。
学生が “楽しい”と思える授業やゼミを続けていきたい
学生の皆さんには、とにかく“楽しい”という気持ちで英語を学んでほしい。教師が生徒の英語学習における不安を左右することはほとんどできないという研究結果が出ています。でも、“楽しさ”は、教える側のやり方次第で大きく変わります。ですので、私はとにかく楽しめる授業やゼミを行うことを大切にしています。例えば「英語表現」の授業ではグループで話し合ってテーマを決めてもらいます。映画や音楽などについて調べたり、留学先について研究してみたり…。興味のあることを深掘りし、まとめたものをプレゼンテーションすることで自然に英語が上達していくのです。
近年の日本は海外からの観光客が増えていますので、今後は本学の学生がそのような方々と交流できる機会を作れたら良いですね。日本にいながら世界各国の方々と交わり、役に立てるような仕組みを考えていきたいと思っています。


Focus in Lab

私のゼミのテーマは「ジャーナリズム」。まずは、私もしくは学生がひとつの英語の記事(新聞、ビデオ、インターネット等)を選び、その記事についてディスカッションを重ねていきました。その後、各学生が興味のあるテーマについての記事を作成。雑誌のような誌面を作る学生もいれば、ポッドキャストの形式で作った学生も。アフリカの女性の苦しみについて調べたり、日本・アメリカ・韓国のコスメについて調べたり…と記事のテーマも手法もバリエーションが豊富。今後のゼミでもジャーナリスティックな記事の作成は続けながら、インタビューやアンケートなどの手法も取り入れ、よりアクティブな場にしていきたいと考えています。
プロフィール
カーディフ大学(英国)芸術人文社会学部 卒業
バーミンガム大学大学院(英国)芸術法律学部 修士課程修了
| 2015年7月 | Master of Arts(バーミンガム大学、英国) |
|---|---|
| 2009年 -2012年 |
武庫川女子大学、近畿大学、龍谷大学 講師 |
| 2012年 -2016年 |
近畿大学英語村 ファシリテーター |
| 2016年 -2019年 |
関西学院大学経済学部 講師 |
| 2019年-現在 | 神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部 講師 |
