


神戸学院大学での4年間には
感情を動かす数々の経験が待っています。
多彩な学びを通じて実際に学生たちが肌で感じ、
成長の種となったきっかけや出来事などを
リアルな想いを紹介します。


指摘が力になった。
法学部 法律学科 4年次生



神戸学院大学には、専門性の高い技能や知識を修得するために、めざす進路にあわせた多様な講座やサポートがあります。今回は、警察官をめざして公務員試験対策コースを受講した川澤さんにお話を伺いました。
あらゆる情報をインプット
本番を想定した
入念な準備にこだわりました
入学後、「自分一人で勉強するよりは、今、何をやるべきかが明確になる」と思い、公務員試験対策講座の警察官コースを受講。警察官コースでは、各教科の試験対策を行いましたが、特に数的処理や判断推理などは基礎を叩き込み、講座で解説を詳しく聞いて学び続けました。学内のフリースペースも活用しながら試験直前までひたすら過去問を数多く解く日々。論文試験の対策では、時事の社会問題や警察白書、各県警・府警のWEBサイトもチェックしながら、世の中がどう変化し、今後どのような力が求められているのか、未来を想像したたくさんのインプットから自分の考えをまとめていきました。また、回答用紙にいかに素早く丁寧な字を書けるかも追求し、消しやすい消しゴムを使うなど細部にもこだわりました。
試験対策で大きな壁になったのは、面接のための自己理解。自分のことがうまく言語化できずにいましたが、担当の先生からさまざまなアドバイスのおかげで少しずつ理解ができるようになり、さらに友人へのヒアリングで自分の強みや特長をメモしながら少しずつ自己理解を深めていきました。

協力とサポートがあって
夢を実現することができました
挑んだ公務員試験では、兵庫県、大阪府、京都府、高知県と四つの試験に合格。資格サポート室や新卒応援ハローワークなどを活用しましたが、この結果は、先生や同じ夢を持った友人などたくさんの人の協力なしでは実現できなかったと思います。一緒に学びあうことで新たな問題の解き方も共有でき、友人の面接練習での受け答えを観察することで気づいたこともたくさんあります。
客観的な意見から学びを得ることもありました。私と同じようにこれから公務員をめざす人には、一人だけではなく、人に頼って仲間と協力しあう勉強方法をおすすめします。あとは、自分が合格するんだという強い気持ちを持つこと。神戸学院大学には、課外講座・資格サポート室、キャリアセンターなど相談しやすい環境が整っています。また、試験の体力テストに向けて、大学併設のジムも活用できます。目標だった公務員試験を突破でき、卒業後は警察官として人々の安心と安全を守っていきます。
理想は人が笑顔になれる犯罪ゼロの社会を実現すること。そのために、パトロールや日々の業務など自分ができることに精一杯取り組んでいきたいと思います。


資格取得で将来の可能性を広げる『キャリア教育センター』
課外講座・資格サポート室では一人ひとりの将来を考えながら、めざす進路にあわせた多様なサポートを提案。また、各学部の専門教育科目にもつながる資格対策講座や公務員試験対策講座などを多数開講しています。就職対策だけでなく、その先のキャリア実現まで見据えた支援を行っています。
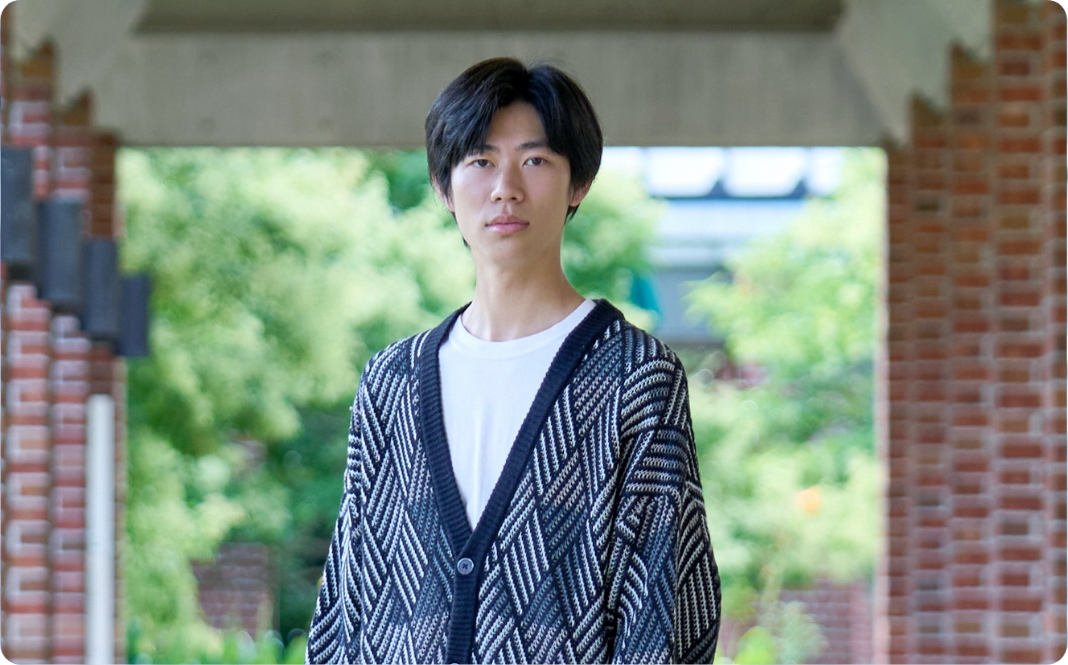

知らないからこそ。
経営学部 経営学科 4年次生



神戸学院大学では、学内での講義やフィールドワークなどのほかにも、地域の自治体や一般企業、団体など連携して学ぶ多彩な社会連携活動を行っています。今回は、震災から30年の節目に株式会社ブルボンと商品開発を行なった高瀬巧弥さんに、その経験を伺いました。
グミ商品を通じて
同世代の若者に何を感じてもらうか
実際の商品開発では、はじめに、コンセプトやターゲット、メッセージ、味、パッケージなどについて約20人のメンバーで意見を出しあって議論を重ね、ブルボンの担当者の方やゼミの先生と何度もミーティングを重ねながらブラッシュアップしていきました。議論の結果、「震災の経験をつなぐ」ことをコンセプトにして、ターゲットは、「震災を直接経験していない若い世代」に設定。商品は若い世代に人気のあるグミに決めました。味については、意見が割れましたが、食べて晴れやかな気持ちになれる爽やかさに酸味を加えたシトラスミックス味に決定することができました。パッケージには「一日一日を大切に生きていこう」という若者へ向けたメッセージを記載。震災を経て、今私たちが生きていることは奇跡なんだという感謝の気持ちを持って、「日々を大切に生きていこう」という想いを込めました。普段何気なく食べているお菓子一つひとつの商品開発の裏には、このような大変な作業があることを実体験できたことは、私にとって、大きな経験になりました。

意外な一言で
さらに想いが強くなりました
生まれてないからこそ、知らないからこそ、私たちがつなぐ意味があるのではないか。お客様からの意外な一言で、さらに私の想いが強くなった気がします。そう感じられたのも、メンバーや企業の方、先生などたくさんの方の協力でつくりあげたから。連携活動は、決して1人ではできない取り組みで、チームワークが不可欠です。今回、メンバー全員の意見を尊重して調整しながら、ひとつの形につくり上げていくことができ、自分自身も大きく成長できたと実感しています。


地域や企業と多彩につながるKGUの『社会連携活動』
神戸学院大学では兵庫県や神戸市などの地域の自治体をはじめ、企業、地域の団体などとともに学外との連携から学ぶ多彩な社会連携活動を行なっています。学内だけでは得られない数々の貴重な経験から課題解決力やコミュニケーション力を身につけ、学生一人ひとりが大きく成長しています。


跡があった。
栄養学部 栄養学科 4年次生



神戸学院大学では、医療や災害、国際、環境など多彩なジャンルのボランティア活動に参加することができ、毎年多くの学生が地域とともに取り組み、貢献しています。今回は、在学時に防災や被災地支援など数多くのボランティア活動を行なっている松本華歩さんに能登半島への被災地支援の経験を伺いました。
実際に手に取ると
複雑な気持ちになりました
一番印象に残ったのは、能登半島地震の被災地支援です。まだ瓦礫が残る3月、私は、被災した家の中の「割れた食器を片付ける」という作業を担当しました。作業内容は理解していたつもりでしたが、実際に割れた食器を手にとってみると、地震が起こる直前までは、普通に“使われていた”食器だと実感しました。こんな思い入れのある食器を簡単に片付けてよいのか? 複雑な気持ちが湧き上がり、手が止まったことも。それでも片付いた後は、依頼された方からお礼の言葉をもらい、やってよかったとほっとした気持ちになりました。被災地に行かなければ、分からなかった被災者の「想い」に触れ、今できることは何かを真剣に考える貴重な経験から忘れてはいけない出来事だと身をもって痛感しました。

気づきや経験を
「食」の世界に生かして
貢献したい
また、被災地訪問の他にも、地域の子どもたちと防災食をつくって食べる活動にも参加。約30人のメンバーをまとめながら、自分の強みや課題、性格を知ることもできました。将来は、この経験を生かし、管理栄養士として「食」で社会に貢献できる人になりたいと考えています。


学生のボランティア活動をサポートする『ボランティア活動支援室』
神戸学院大学では学生とボランティアをつなぐ懸け橋として、両キャンパスにボランティア活動支援室を設けています。活動を支えるボランティア活動支援室には学生スタッフが所属し、医療班、災害班、国際班、子ども班、広報班、環境班の6つのジャンルに分かれて企画を考え、職員と協働して事業を運営しています。


世界の壁が消えた。
現代社会学部 社会防災学科 4年次生



神戸学院大学には、留学や将来のビジネスに生かしたい、世界の人々とコミュニケーションを深めたいなど学生のレベルや目標にあわせて英語力を伸ばすプログラムがあります。今回はEnglish Plaza(い〜ぷら)を利用して留学経験のある真砂さんにお話を伺いました。
「暮らしの一部」に
変わっていきました
「い〜ぷら」では、ミスをしてもOKというポジティブな雰囲気の中、恐怖心もなく、リラックスしてコミュニケーションができるので英語力が飛躍的に伸びていくことを実感。自分でも1日1フレーズを使うなど小さな目標を設定して地道に取り組んでいきました。自宅に帰ってからも映画やインスタで知った英単語を普段から覚えたりするなど、英語が「勉強するもの」から「暮らしの一部」になったことが、大きな成長ポイントになったと感じています。

英語力も着実に成長
「もっと話したい」と
思えたことが財産
「い〜ぷら」で学んだ後、アメリカへ4カ月の語学留学を経験。現地の会話の速さに最初は戸惑いましたが、次第に慣れ、現地では多くの友達ができました。「い〜ぷら」であらゆる国籍の先生方から多彩なアクセントに触れた経験も大きかったと思います。「い〜ぷら」は、世界各国の文化を理解でき、世界に活躍できるきっかけをもらえる場所。「英語をもっと話したい」と思わせてくれたことが一番の財産です。英語ができると行動が変わり、世界への壁が消え、見える視野も広がります。将来は海外で暮らす夢もあるので、さらに英語スキルを伸ばしていきたいと思います。


外国人講師と英語を楽しく学べる『English Plaza(い〜ぷら)』目標を設定して英語力を身につける『神戸学院カレッジ』
神戸学院大学ではカリキュラム以外にも英語力を伸ばす独自のプログラムがあります。ゲームやイベントなどを通じて外国人講師と楽しみながら英語力を伸ばすEnglish Plaza(い〜ぷら)。TOEIC600点以上などの目標に向けた英語力を身につける『神戸学院カレッジ』では個人のレベルにあわせて受講可能です。


言葉が力になった。
経営学部 経営学科 3年次生



学生ならではの視点でオープンキャンパスを企画・運営する学生スタッフ「オーキャンズ」。
イベントの企画から準備、当日の案内などを学生が主体となって取り組んでいます。300人以上のオーキャンズスタッフをまとめるポートアイランドキャンパス代表の早﨑紗千子さんにオーキャンズの経験を伺いました。
夏のオープンキャンパス
アンケート時の親子の言葉が嬉しかった
オーキャンズは、高校生や保護者の方が気になることについて、普段の様子をありのままに話すので、私たちの会話を通じて安心していただけたのだと思います。実際に、オーキャンズの存在が入学の決め手になった高校生がいることや、保護者の方から、「キャンパスの雰囲気は歩けばわかるけど、学生の姿は、学生さんからしかわからない」「オーキャンズの方から詳しい説明を聞き、この大学に通わせたいと思った」という声があり、頑張って企画してよかったと実感しました。オーキャンズ一人ひとりの姿が、自然と学生の見本になっていたのかもしれません。また、先輩後輩をペアにして、アドバイスをもらいながら話す練習を行っている成果があったのだと感じています。

それが自分を見つめ直すことにもなっています
私はこれまで、代表という立場の経験がありませんでしたが、代表となったことで人をよく見るようになり、またそれが自分を見直すきっかけにもなりました。
代表の役割の中に、各メンバーへの仕事の割り振りがありますが、その人の性格や長所を把握することが重要です。そこで、メンバーをよく観察するようにしています。また、話してみないと良さがわからないこともあるので、多くのメンバーと積極的に自分からコミュニケーションをとりながら相手のことを理解するように心がけています。
オーキャンズの魅力は、先輩や後輩に関係なく、とにかくたくさんの仲間と話せること。「そっちの学部はどんな感じ? みんな学生生活頑張ってる?」など、他学部の友達が自然とでき、他学部を知るきっかけにもなっています。今、本当に貴重な経験をさせてもらっているので、将来必ずこの経験を生かしたいです。4月から、人的資源が専門のゼミに所属し、マネジメントに興味を持ったところなので企業の人事や人材開発部門で生かしてみたいと考えています。
神戸学院大学の魅力は、何といっても整備された学修環境。訪れてもらえば、キャンパスの居心地の良さを感じてもらえると思います。これからも、もっと多くの方に神戸学院大学の魅力を発信していきたいです。


オープンキャンパスで大学の魅力を伝える「オーキャンズ」
ポートアイランドキャンパス・有瀬キャンパス合わせて500人以上のメンバーが所属する学生団体。オープンキャパンスを企画・運営し、在学生の視点から神戸学院大学の魅力を発信しています。当日はピンクのポロシャツを着て、来場者をお迎えします。


伝わらなかった。
薬学部 薬学科 3年次生



学部学科や大学の枠を越えてチーム医療を学ぶ専門職連携教育(IPE)。
それぞれ専門の異なるメンバーがお互いのスキルや役割を生かして質の高い医療ケアを実践的に学びます。
IPEの授業に参加した学生さんのリアルな経験を伺いました。
専門性の違いから生まれる
齟齬を実感しました
また、メンタルヘルスケアの授業では、一般の方だけではなく、医療従事者自身にとってもメンタルヘルスが大切なのだと学びました。チーム医療では異なる専門知識を持ったメンバー同士が互いを尊重し、情報を正確に報告することが患者さまへの最適な治療につながっていきます。
IPEの授業中にハッと気づいたのはグループワークを行う中で、薬学部では当たり前のように使っていた専門用語がチームメンバーに伝わらなかったことがあり、チーム医療の現場でも同様の齟齬が生まれる可能性があると実感しました。お互いの知識や専門性を理解して、相手にいかにわかりやすく、正確に伝えるか。メンバー同士の繋がりを大事にしながら、メンバー全員で患者さまへの最適なアプローチを追求する環境づくりを学んでいきました。

リスペクトし合いながら
めざすゴールは「患者さんの笑顔」
お互いの専門は違っても「患者さまの笑顔」というゴールは同じです。メンバー同士でお互いにリスペクトし合うことや信頼することが大切だと授業を通じて感じました。そのためには、自分が思ったことは自分の中で留めずにメンバーに投げかけてお互いに共有することを徹底し、チームのコミュニケーションを円滑にすること。
将来は、この経験を活かしてチーム医療を推進する医療従事者の一人として、患者さまの生活の質を高める医療の実現に貢献していきたいと思います。


チーム医療のスキルを学べる専門職連携教育(IPE)
神戸学院大学では、薬学部・栄養学部・総合リハビリテーション学部・心理学部に加えて神戸市看護大学と連携した教育プログラムを実施。多職種が協働するチーム医療の即戦力となる人材を育成しています。














